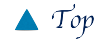📓 『カタカムナ』 全80首の意味−第34句の解説
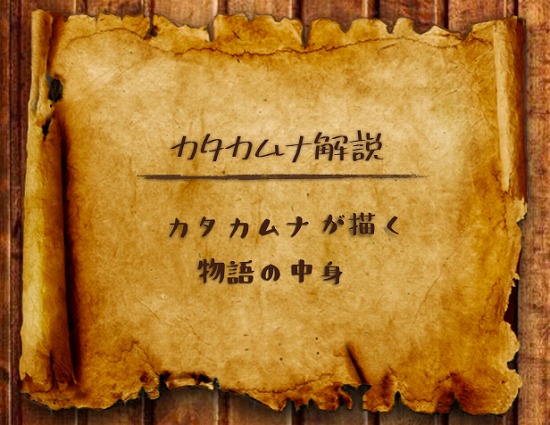
『カタカムナ』第34句 今回は、この句の訳を武器に『日本神話』の謎に切り込んでいきます。
『古事記』の内容そもそも、『イザナギ&イザナミ』が天の日矛で海をかき混ぜて、地を造った…… と描写されている『日本神話』ですが、あれっていつの時代のことだと思います? 『縄文時代』のちょっと手前? それとも、さらにさかのぼる、太古の原始時代?? 『日本神話』で描かれているエピソードは、いつの時代の話なのか? 皆さんも興味のある、面白そうなテーマでしょう? その謎をこの『カタカムナ』第34句を武器に、今回解き明かしてしまいます。 ・ ・
イザナギ&イザナミの二人の神様が、 「よし決めた! この場所に天に似せた地形を作ろう!」と二人で雲の上から「天の日矛」で海をかき混ぜたら、そこから雫がしたたって、【おのころ島】ができた!
『カタカムナ』 全80首の意味−第34句の解説
📓 【原文】
【漢字に直すと?】『カタカムナ』 第34首
アマツ ミソラノ アメ ヒトツハシラ サド オホヤマト イヤシロチ タニ キビコ アキツノ イヤシロ スベ シマ カサネ オホタマル ワケ オホコトオシヲ トワ チカ フタヤヒメ
『カタカムナ』 第34首 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-🔎 【この句の意味は?】天津 御空の 天一柱 佐渡 大 倭(大和)弥盛地 谷 飢彦 空き津 の弥盛 術 島 重ね おほ賜る理由 多言教神を 永遠 地下 二夜姫(二毛作)
『カタカムナ』 第34首 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-高天原から 光の柱が降りて造られた 遠い彼方まで この大倭の影響力が届くなら 谷(不毛の地)の食糧難の民も 助けられる その知恵を『教師の神』がお告げで降ろした理由は? 『神の知恵』を各地に伝えてこそ豊かな国となれるからだ
今回の訳を通して『日本神話』の謎に切り込んでいきます
ココは、私がまとめます。 いつもなら、神様に質問しながら「ああ、そういうことだったのか!!」と、皆さんと同じように驚きながら、書き留めているのですが、 今回に限って言えば、何があったのか? のイメージが一瞬で降りてきたのです。 消えないうちに、見えたイメージを急いでまとめます。 ・ ・
天地創造の描写。『おのころ島』が造られたときの様子。 見えたイメージによると、これはどうも事実っぽい。
私に降りてくる神様のメッセージも、天地創造の描写については、比喩的表現ではなく、『事実』として語っているので、見えたイメージと降りてきた説明を突きあわせてみても、矛盾はない。 天地創造の描写は、カタカムナの中でも複数の句で描写があるものの、全てが一つの方向性を指している。 ・ ・ すると、大倭の地(岡山・兵庫県沿岸部)は本当に神様にとって特別な地であったことがわかる。 その地の統率者の子孫(何代後か? までは分からない)は、 後に自分たちのことを『イザナギ&イザナミ』の〝国つ神〟と名乗るようになって、権力方面に流されてしまったモノの、 初期の統率者に対しては、神様は絶賛擁護 している。高天原から地に向けて穴が空いた。巨大な穴。 そして、光の筋が伸びた。それは霧のような幻想的な光の筋。 地上は7日間霧に包まれ、何も見えなくなった。 明けて、晴れ間がのぞいたとき、そこには今までなかった新しい島が、『完成形』の形でできあがっていた。 神はいたく気に入った。自分で名前をつけた。(神名祝ぐ) それが、「おのころ島」 日本神話はここからスタートする。日本の歴史も……。
初期の統率者は、弥生時代に日本に稲作文化を広めたグループこの知識と造田技術が、もっと広い範囲に届けば、日本の民はもっと豊かになっていくと、神様が支援をしている。 彼らは他の地域に向けても、無償で神様から教わった『知恵』を与えていた。 ・ ・ なので、近畿地方の一部だけ治めていた、稲作知識を持つ大倭勢力が、四国や佐渡方面(上越地方)まで影響力を広げていくことは、『弥盛地』と言って、神様も肯定している。 〝弥〟とは、ますます栄える! という意味 なので、大倭勢力の影響力が遠くの地まで及ぶ過程で、途中の土地の人々もますます栄えていく……。 そしてその活動で……
谷 忌曾孫 空き津 の 弥盛 術貧しい地域の人たち、土地がうまく整地できてないところの開拓の仕方、生産能力の上げ方を、神様から巫女(シャーマン)のへのご神託を通して、その土地に適したやり方を、どんどん教えていっている。 孫の代まで作物が育たないような、悪い土地に対する五穀豊穣の再生術 各地域に出向いていって、効率的な生産のための、生産プロセスの最適化の提案って…… まるでコンサルタントみたい(笑) ・ ・ こうして謎が明らかになっていく過程で『日本神話』の神話時代とは、いつの時代のことを指すのか? 『カタカムナ』の訳を通して、少しずつ絞り込めてきました。
『日本神話』の時代背景は、縄文末期か弥生初期が起点のようもちろん、これは『神話の起点』のお話。 それ以前の縄文時代にも日本には土地があって、そこに人も住んでいたことは誰でも知ってるし、 そもそもキリスト教の『アダムとイブ』のお話も、日本神話の『イザナギ&イザナミ』のお話も、恐竜時代のことが想定外。 なので、『神話の起点』は必ずどこかにある。それは一体、どこを指すのか? ・ ・ なので、あくまで『おのころ島のイベント』を起点とした神話の始まりは、縄文末期か弥生初期 なのではないか? それから相当な時間が流れ、彼らがやって来た。 彼らから見た、『日本神話』の時代は、全部、弥生時代(紀元前250年前後)に収まるのではないか? このときに火山噴火があり、そしてアマテラス&スサノオのせいにされているので、卑弥呼の生きていた時代と、火山噴火が時代として一致する。 ・ ・ ……いつものように、どこまでが天から降りてきた知識で、どこからが自分で考えたことなのか? 境界線は自分でも分かりませんが、現時点ではこのような認識です。 ちなみに、いつもの伝家の宝刀、『神様に泣きつく』の技では、今回は降りてこなかった。 だいたい今までの流れからすると、こういう『降りてこない』ときというのは、思考の流れを記録させたかったから、わざと教えなかった……というケースだったんですよね。 今回もそうなのかも?🔎 カタカムナのヒントで解いた『古事記』の用語解説
❏ 【大 倭って何?】 ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-🔏 いつものように『漢字の間違い訂正』 シリーズ
・ 大 倭(オオヤマト)……(皇・大和) ・ 忌曾孫(キビコ)……(飢彦)近畿地方の一部地域のことを、 現地の人は『おおやまと‐ひだかみのくに』と呼んでいた。 例によって古文献では【大倭日高見国】と誤記されているが 本当の字は『皇倭日高神の国』が正解。 太陽神、天照大神のお膝元の「神の民」の国 という意味。 ここから転じて、『天照の元の御国』→『日の本の国』→『日本国』となった。 大倭は、関東の常陸国を指すのでは? という説もあるが、それは間違い。見て分かるように、大倭(皇倭)とは、のちの大和朝廷〜神武天皇につながる勢力のこと。❏ 【忌曾孫って何?】 ・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-わけの分からない漢字があてられているが、タダ単に 〝食糧難の人〟の意味で… 『飢彦』 『彦』は通常ポジティブな意味合いで用いられることが多いものの 今回はタダ単に『彼ら』の意味で使われている。『カタカムナ』 全80首の意味−第35句の解説